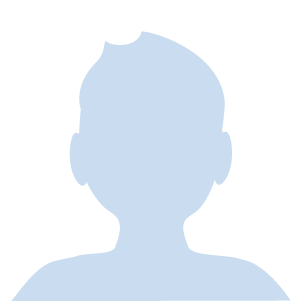初心者から中級者向け!【四季報】株式・財務・キャッシュフローの見方をわかりやすく解説
この記事はPRを含みます
四季報ってどんなもの?どんな時に使うの?
四季報は、東洋経済新報社が3ヶ月に1回発刊する雑誌(3、6、 9、12月刊)です。
四季報に書かれているのは、株式を自由に売買できる証券取引所に上場している全企業の
- 特色
- 注目材料
- 業績
- 財務内容
- 株価の動き
です。
かなりコンパクトに描かれてるため、簡易的に銘柄を判断するのにかなり役立ちます。
四季報記者の徹底取材により、企業寄りでも証券会社寄りでもない中立的・客観的な分析に定評があります。
全上場企業を1冊にまとめた雑誌は世界で唯一無二で、個人投資家だけでなく証券会社・金融関 係のプロや公的機関からも絶大な信頼を寄せられています。
出典:会社四季報 徹底活用術
四季報の中の株式・財務・キャッシュフローとは
四季報の株式・財務・キャッシュフローでは財務状況を示す指標がたくさん散りばめられているので、見れるようになると銘柄選びに重宝します。
例えば、
- 急激に株価が下がった理由が理解できる
- 日経平均株価は大暴落したのに自分が投資している銘柄の株価が変わらない
ということもよくあります。
投資をするときに倒産しないか、今後伸び代があるかはやっぱり知っておきたいですよね。今後の成長に期待ができる企業を見つけるために株式・財務・キャッシュフローの見方を解説していきます。
株式の見方

発行済み株式数
実際に発行された株式の総数で自己株式は除外されます。
単位100株
1回売買するときの単位のことです。
・1株300円なら
・1回の売買は30,000円(300円×100株)〜
となります。現在は国内株式の売買単位は銘柄を問わず、100株に統一されています。
時価総額
「株価×発行済株式数」で計算されるため、会社の規模がわかります。
日本で時価総額が大きい企業
・トヨタ自動車
・三菱UFJフィナンシャル・グループ
・ソニーグループ
・日立製作所
‥などです。
これでわかる通り時価総額が大きい会社は会社の規模が大きくなります。
優待
巻末一覧に株主優待制度の具体的内容があることを示します。
貸借銘柄
空売りができる銘柄のことです。
A社の株が下がると思ったら先に売って後で買い戻すことができます。
財務の見方

総資産
貸借対照表(企業の資産・負債・純資産がわかる表)の資産部の合計で、企業が持っているすべての資産合計のことをいいます。
現金や預金だけでなく投資信託・株式(証券)・不動産・車なども含みます。
例えば、A社の総資産は簡易的には下記のように表記され、すべての資産の合計が示されます。
| 現金 | 6,800百万円(68億円) |
| 機械 | 400百万円(4億円) |
| 土地 | 100百万円(1億円) |
| : | : |
| 総資産 | 153,000百万円(1530億円) |
自己資本
株主資本とその他包括利益累計額の合計のことを言います。
グループ企業は親会社だけの株主資本の合計が示されています。
株主資本とは「株主が出資した資本」と「資本を使って生じた利益」のことを言います。
例えば
・Aさんが500万円B社に投資して
・250万円の利益が生まれた場合
・株主資本は750万円
となります。
▲は債務超過を示します。
債務超過とは企業の負債総額が資産総額を上回る状態を指します。
財政状態の不健全な状態を意味し、倒産のリスクが高まります。
自己資本は株主が出資した「資本金」のほか、「資本準備金」「資本剰余金」「利益準備金」「利益余剰金」などで構成されます。
そのほかの包括利益累計額とは、貸借対照表(企業の資産・負債・純資産がわかる表)の純資産の部分に表示される勘定科目の一つで、その他有価証券評価差額金、繰延ヘッジ損益、為替換算調整勘定、 退職給付に係る調整累計額、土地再評価差額金などの合計を言います。
自己資本比率
これは返済不要な資本が多いと倒産リスクが低くなるためです。
例えば、
- A社(自己資本比率70%)
- B社(自己資本比率20%)
を比較するとB社は借入に依存していて不安定ということができます。
そのため自己資本比率が高い方が企業の財務は安定していると言えます。
自己資本とは、企業が自力で調達した資金のことで、株主から集めた資金や利益の蓄積などが含まれます。自己資本は基本的に返済義務がありません。
資本金
株主が会社に出資した金額や、事業を始めるための元手となる資金のことです。
この資本金を元手に事業を展開していきます。
資本金が多い会社というのは出資が集まりやすく、社会的に信頼度が高いことが多いという特徴があります。
債務超過を回避したり利子を払う必要がなかったりと体力のある会社とみなされるからです。
利益余剰金
企業が生み出した利益を積み立てたお金で、会社内部に蓄積されているものを指します。
利益が増えれば利益剰余金は順調に増えますが、赤字決算が続くと利益剰余金は減少し、いずれマイナスに陥ります。
▲は欠損を示します。
有利子負債
金利をつけて返済しなければならない負債のことを指します。
残高が大きいほど、財務体質が悪くなります。
貸借対照表で算出できない場合は→「:」と示されています。
この財務項目の見方に関しては銀行、証券会社、損害保険会社、生命保険会社、ノンバンクは除いています。
ここからは中級編です。飛ばしても構いません。
<>の中身は直近の本決算もしくは四半期決算時点での財務データであることを示します。
- 連:連結決算、日本方式
親会社だけでなく、国内・海外子会社および関連会社を含めたグループ全体の決算方法のことです。連結決算では、企業グループ全体の貸借対照表や損益計算書を連結財務諸表として公開しています。 - ◎:連結決算 米国SEC方式
米国式の会計基準です。日本企業が、ニューヨーク証券取引所に株式を上場するためには、米国式連結財務諸表を提出しなくてはならないためこの方式で連結決算が表示されています。 - ◇:連結決算 IFRS方式
「国際財務報告基準(International Financial Reporting Standards:IFRS)」とは国際会計基準審議会(International Accounting Standards Board:IASB)が策定する会計基準です。
国際財務報告基準は、会計制度は国ごとに異なりますが、資本市場のグローバル化が進み、どの国の企業でも実態を把握できる世界共通のモノサシが必要になってきました。各国バラバラな会計基準を統一基準に収束する動きが出てきています。
- 単:単独決算 日本方式
企業には、親会社、子会社(または関連会社)が、1つのグループを形成しているケースがあります。企業グループ全体の決算のことを「連結決算」、個々の企業の決算のことを「単独決算」と呼びます。 - □:単独決算 IFRS方式
指標の見方

ROE:自己資本利益率
「自己資本を使ってどれだけの利益を稼いでいるか」をいいます。
自己資本がマイナスなら「-」と表記されます。
株主が出資したお金を元手に、企業がどれだけの利益を上げたのかを数値化したもので、「企業がどれぐらい効率良くお金を稼いでいるか」を示す重要な財務指標です。
ROA:総資産利益率
「総資産を使ってどれだけの利益を上げたか」を示します。
企業に投下された総資産(総資本)が、利益獲得のためにどれほど効率的に利用されているかを表します。
決算期変更があった場合は→「:」と示されています。
・実績ROE=純利益÷(期首と期末の平均自己資本)×100
・予:予測ROEと予測ROAのことで「予測純利益÷直近本決算もしくは四半期末自己資本または総資産」
調整1株益
会社が持っている発行されていない株式(潜在株式)が全部発行されたと仮定した時の1株あたりの利益をいいます。
最高純益
過去最高の純利益のことをいいます。
()内にいつの決算期で最高純益を出したかを示します。
設備投資額
年間の工事実績額を示します。
建物や機械などの有形固定資産と商標などの無形固定資産にどれだけ投資したかを示します。
減価償却費
有形・無形固定資産を購入した金額を耐用年数に応じて計上したときの年間償却実施額を示します。
・予:有形のみの場合があるので注意が必要です。
研究開発費
研究・開発・試験のための人件費、原材料費、設備装置購入費などをいいます。
キャッシュフローの見方
営業CF:営業活動
営業キャッシュフローが潤沢な企業ほど、外部からの資金調達に依存する割合が少ないため、経営が安定します。
本業でどれだけのお金を稼いでいるかがわかります。
投資CF:投資活動
企業が投資活動にどれだけ力を入れているかがわかります。
マイナスでも将来のための積極投資の可能性がありますし、プラスでも現金が足りず株や債券、土地などを売った可能性があるので一概に良い悪いは判断できません。
IRを確認するのがおすすめです。
財務CF:財務活動
出資や金融機関等からの借入など資金調達の流れがわかります。
プラスなら借入金が増えているということでマイナスなら借入金を返済している、負債も減っていることを表ます。
▲はキャッシュの流出、無印は流入を示します。
現金同等物
上記3CFの結果、手元に残った現金や預金などの期末残高を示しています。
左が本決算における額、右の()内が前期の年額です。
最後に
やみくもに投資をするのではなく、企業の状況について正しく認識して投資をしましょう。少しでも投資をするときの銘柄選びの手助けになると嬉しいです。
できるだけ理解しやすい言葉を選ぶので、勉強熱心で意欲のある投資初心者にもどんどん伝わっていくと幸いです。